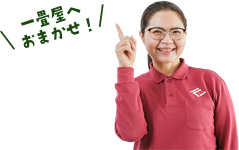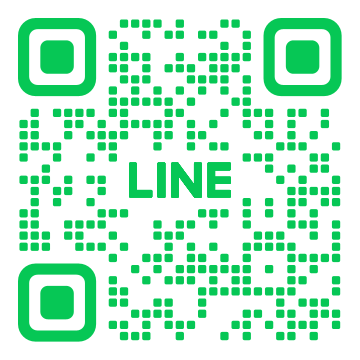畳のこと色々の一覧
いぐさ成長日記その2 4月編
駆け込み需要で激動の3月をすぎ、4月の半ばやっと産地八代に行くことが出来ました。
今日は、一畳屋一番人気の畳表の生産者倉井さんのところへ

この日は、追肥の真っ最中。
高級な有機肥料をふんだんにまいております。
こしの強いイグサを作るためには欠かせない作業です。
現在八代で生産されているいぐさは、大きく分けて2種類あります
倉井さんは今では3割しかなくなってしまった、在来種の生産者です。

長年のお付き合いで、私たちが提供したいものもよく理解していただいており、
年間を通して安定的な商品が提供できるのも倉井さんという同志がいてこそです。
昨年分の倉井さんの畳表は売り切れました。
今年の新草の予約をして帰路につきました。
今年のいぐさも順調に育っております。
8月~9月畳表として出来上がるのが楽しみです。(光)
古畳 古ゴザ差し上げます!!
こんにちは、一畳屋です。
日々畳の表替えや、畳の新調の入れ替え工事をしていますと、
古ゴザや、古畳がたくさん出ます。
古ゴザ、古畳を無料で差し上げます!!
古ゴザとは、畳の表替えの際に使わなくなったゴザ(畳の表面のこと)です。

古床とは、使わなくなった古畳のことです。
古ゴザはまだきれいなものは、お花見シーズンや行楽シーズン、運動会などのレジャーシート代わりや、
農作業の敷物や、マルチング材代わりに使ってらっしゃる方もいます。
畳床は、藁の素材が多く果樹園に敷く方や、牛の緩衝剤などに使えるとのこと。
無料で差し上げますので、あなたのアイデアで思い思いにお使いください(笑)
お気軽にお問い合わせください。
場所:熊本県合志市栄3415-11
電話:096-348-3176
担当:亀井 光子
いぐさ成長日記その1
いぐさは、植えてから刈取りまでにどのくらいの時間がかかるのでしょう?
ホウレンソウ、キャベツなどは種から3,4か月で収穫ですが、いぐさは、元苗を植えてからなんと1年7か月もかかります。
これが、ポット植えの赤ちゃん苗(来年7月に収穫分)影写りこんですみません。
こちらが、畑で育てている赤ちゃん苗
1月29日に撮影した、いぐさの田んぼ、一番寒い時期ですね。
根がしっかり張るほど、良いイグサになります。
土づくりが重要です。
続いて2月23日撮影のイグサの田んぼ
1月の写真と比べると、大分草が伸びて青々してきました。
根も順調に張っています。
よーく育って、良い畳表になってよー(笑)と願いつつ圃場を後にしました。
また、来月に生育状況はお伝えしたいと思います。(光)
いぐさ製織体験!!
先週の土曜、イグサ農家さんで畳表の製織体験をしてきました。
畳の材料畳表は、畳屋さんが作る物、と思ってらっしゃる方も多いかもしれませんが、
農家さんがいぐさの収穫から、泥染め、乾燥、
製織、つまり畳表に織り上げるまでを一手に引き受けてくださっています。

いぐさは、収穫したあと、泥染め、乾燥し上の写真のような形で保存されます。
いぐさを織る前に、製織の際にいぐさが折れてしまわないように適度に加湿します。
機械で長さを選別した後、焼けや、折れがないか人の目で確かめ、
長さをそろえ、織機にかけます。
織機には、人が付きっきりで、機械に異常はないか、きちんと織れているかなどをチェックします。1日で織れる畳表は、10枚程度です。高級品になると、1日4枚程度しか織り上がりません。
中国産の畳表などに押され価格が下がり、熊本のいぐさ農家さんは10年前の半分以下に減ってしまいました。
以前、大手着物メーカーの社長の公演を聞いた際「伝統産業は産地と市場両方作っていかないと無くなってしまう」という言葉が、私の胸の中にはずっとあります。
お客様に喜ばれるのはもちろんですが、いぐさ農家さんも喜んでいぐさを作り、後継者に安心して継承していけるようにしていきたいと改めて思いました。
この研修会には全国の畳屋さんと産地の農家さん、問屋さんが参加しております。そこには、畳を愛する熱い仲間がたくさんいました。
一畳屋だけで、これをやるのは無理かもしれませんが、全国の仲間たちと共にいぐさの産地を盛り上げていきたいと思いました。(光)
6人の畳一級技能士!!
昨日のブログをご覧になった方は、少しばかり重複する内容で失礼いたします。
一畳屋には、4人の畳1級技能士がいたのですが、昨年さらに2人が合格し、畳1級技能士は合計6人になりました。

畳一級技能士の試験は、実技と筆記があり実務経験7年以上の畳職人に受験資格が与えられる、国家資格です。
品質向上のためと、従業員のモチベーションアップのため一畳屋では、畳一級技能士の資格取得支援をしています。




畳技能試験は、5時間半で、床切りから縁の縫付けまで1枚の畳を5時間半で仕上げるというものです。最近では、畳屋といっても機械で生産するのが主流で手縫いで畳を作ることはほとんどありません。
しかし、より良い畳の仕上がりを追及するうえで、筆記試験の勉強や、畳を手で一枚仕上げるという練習はとても良い機会になったと思います。
一級技能士をとったことで、本人たちにも自身が付き、仕事に対する態度にも一段と磨きがかかったと思います。
畳歴40年を超える社長の弁を借りると「一級技能士をとってからがスタートのようなもんだ」ということなので、おごらず今後ともお客様のために精進していきたいと思っております。
作業の標準化 作業マニュアル検討会
忙しい年末を終え、1月は一畳屋で一番仕事の少ない時期を迎えます。
皆の頑張りもあり、繁忙期もほとんどクレームもなく乗り越えることが出来ました。
新しいメンバーも増えたということで、機械メンテナンスのため機械が一日止まる日を利用して、
日々の終礼では深堀出来ない、新人さんに教える内容の統一、
さらなる技術の向上、お客様満足度UPを目指して、
先日作業の標準化と、作業マニュアルの検討会を行いました。
まずは、事務所で現段階の作業を確認、「もっと効率的なやり方はないか」、「新人さんへの教え方はどのようにしたら良いか」など、全員参加で議論が飛び交います。
議論をふまえて、工場で検証作業。
丸一日かけた会議も終わり、着々と決めたことを実行する日々です。
八代視察
1月29日 八代にイグサ農家さんの視察に行ってきました。
今回お伺いしたのは、倉井さんと草野さん2件の農家さんです。一畳屋の主力商品を提供していただいている農家さんで、今では少なくなってきた、在来種のイグサを表皮が強く、お客様に長く使っていただけるようにという信念のもと、イグサつくりに情熱を燃やしていらっしゃいます。
畑に植えられた来年の苗、ここから上のイグサのように、原材料として使えるようになるまで1年7か月かかります。
これが、今年の苗。根が真っすぐ伸び強いイグサに育っていきます。
いぐさは、刈り取って終わりではなく、泥染め、乾燥、選別、織り、仕上げなど様々な工程を経て私たち畳店が使う、畳表となり。さらに畳屋が、畳の状態に仕上げお客様のお部屋に敷きこみます。
イグサの選別作業
いぐさ専用織機で織り上げます。
だいぶ工程省きましたが、完成した畳表です。
畳には、農家の愛情と、畳屋の愛情が詰まっています。そのうえ空気をきれいにし、リラックスさせてくれっます。改めて、畳って世界に誇れる素晴らしい敷物だなと思いました。(光)
一畳屋のチラシ
一畳屋のチラシはここ数年、顔写真入りのものを使用しています。
 (最新チラシ表)
(最新チラシ表)
.jpg) (最新チラシ裏)
(最新チラシ裏)
社長・常務・三兄弟、そして社員たち。顔を出しているので、自分の仕事により責任感がわいてきます。
寝ている赤ちゃんは、長男の一人娘!!まさに家族総出演(笑)
ずっと、チラシをとっておいてくださるお客様や、常務や社長の同級生や知人が写真を見て注文してくださることもしばしば。
今日も、常務の高校時代の先生の所に見積もりに行ってきました。常務の高校の卒業アルバムまで見せていただ来ました。
先日も常務の同級生のお家で、自家製のお野菜をいただきました。
そんな信頼にこたえるいい仕事(お客様に満足していただける仕事)をしていきたいです。
次のチラシあたりには、私長女の写真も、のるかな・・・・(光)
ハート畳 円畳
畳といえば、長方形や正方形が一般的ですが、最近は様々な形の畳に挑む畳屋さんも多いようです。
私も先日、畳で楽器を作っている畳屋さんを見ました。
自分の会社じゃなくても、畳のことがテレビで取り上げられると何となく嬉しくなってしまします。
一畳屋でもこんな畳作っています!!
ハートの畳、{長男慎一郎はこの畳を、結婚式のウェルカムボードとして使いました。(^~^)}

<写真は年を取るごとに似てきている、常務(母)と社長(父)です>
円の畳

円の畳は円形に畳を作るのも難しいのですが、よーく見てください!!
縁の部分の柄合わせ(専門用語で紋合わせ)もかなーり難しいのです。。。
力作2本立てですが、作ったのはもちろん我が社の看板息子。3男喜三郎です。

ちょっと変わった畳のオーダーも承っておりますので、お気軽にお問合せください。(光)